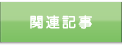【2011.12.12】 民法改正の趣旨を無視する裁判官・調査官の 是正を求める最高裁への意見書
平成23年6月3日に民法766条の改正が交付されました。その民法改正の趣旨については、6月6日、8月3日の2回にわたり、全国の家庭裁判所や高等裁判所に対し、最高裁判所家庭局からの通知・通達という異例の形で周知されました。
しかしながら、下級裁判所の一部裁判官や家庭裁判所調査官は、これらを無視し、従来の運用を変えていないことが明らかになってきました。
酷い調査官調査や、審判などの事例を示しながら、運用の是正を求める意見書を最高裁判所長官および家庭局長宛に送付しました。
民法改正の趣旨を無視する裁判官・調査官の 是正を求める最高裁への意見書(pdfファイル[約45Kbyte])
竹﨑博允 最高裁判所長官 様
豊澤佳弘 最高裁判所 事務総局家庭局長 様
代表 藤田尚寿
私たちは、親子の面会交流を実現する全国ネットワーク(親子ネット)という市民団体です。離婚や別居後に、我が子との面会交流が絶たれている非監護親を中心に、270名の会員を有しています。
去る平成23年6月3日、民法766条の改正が公布されました。そして、その民法の改正の趣旨については、6月6日、8月3日の2回にわたり、全国の家庭裁判所や高等裁判所に対し、最高裁判所家庭局からの通達という異例の形で周知していただきました。このような形で、子どもの監護に関する事項については、子どもの利益を最優先すべきとする条文の趣旨を全裁判所に周知徹底していただいたことについては大変感謝しています。
しかしながら、一部の裁判官・家庭裁判所調査官(以下「調査官」という)などの家庭裁判所に勤める公務員は、従来からの運用を全く変えようとしません。その事実が次第に明らかになってきました。
その点について、2つの典型的な事例で補足しながら、以下の6点の問題点を指摘し、その運用を改めることを通じ、下級裁判所の本質的な体質改善を求めます。
(A) 面会交流事件(平成22年(家)第2796号)横浜家庭裁判所
家事審判官:庄司芳男
家庭裁判所調査官:松本祐里、越 裕美
上記面会交流の抗告事件(平成23年(ラ)第1298号)東京高等裁判所
裁判長裁判官:松本光一郎
裁判官:高野輝久、齊木利夫
| 子の監護に関する処分(面会交流)事件(平成22年(家)第2796号)の調査官調査報告書 |
(B) 監護者指定事件(平成23年(家)第599号)千葉家庭裁判所松戸支部
家庭裁判所調査官:佐藤 一、上野礼絵
| 監護者指定事件(平成23年(家)第599号)の調査官調査報告書の意見部分 |
| 監護者指定事件(平成23年(家)第599号)の調査官調査報告書の佐藤一調査官、上野礼絵調査官の意見に対する反論 |
(1)法律及び国会の審議を全く無視している
御存じのとおり、国会における法案審議の中で、以下のとおり民法改正の趣旨や「子どもの利益」に基づく裁判の基準等についての答弁が法務大臣からなされたところです。
| ① | 監護権・親権を一方の親から剥奪することを目的とする虚偽の配偶者暴力 (DV)の訴えを助長することがないよう、DV 防止法上の保護命令は適正な手続きの下で行われるべきこと |
| ② | 子どもの連れ去り及び引き離しは、場合により「児童虐待」に該当し、当該行為を働いた親は、裁判所の監護者指定時に、不利な推定が働くこと |
| ③ | 面会交流に積極的な親は、裁判所の監護者指定時に、有利な推定が働くこと |
| ④ | 監護者が面会交流の取決めを正当な理由なく破ることは、監護者変更の重要な要素となること |
| ⑤ | 「寛容性の原則(Friendly Parent Rule)」に基づき、一方の親と子どもとの面会交流について、より頻繁な面会交流を認める提案をする親を監護者として指定する方法は、一つの方法として考慮されるべきこと |
| ⑥ | 「継続性(現状維持)の原則」により、子どもの連れ去り・引き離しを追認して監護者を決定することは許されないこと |
加えて、法務大臣からは「可能な限り家庭裁判所は親子の面会交流ができるように努めることが、この法律の意図するところである。家庭裁判所の調停・審判で、より一層こうした方向で努力がなされることを期待する」(4月19日衆議院法務委員会)など、婉曲ながら、これまでの家庭裁判所の実務に根本的な反省と転換を迫る答弁が繰り返しなされたことも御承知のとおりです。
今回の改正は、民法第766条の条文の趣旨を明確化するものであり、国会における法務大臣等が答弁により明らかにした当該条文の解釈は、改正民法の施行前においても有効であることは言うまでもありません。
私たちは、これらの一連の経緯を踏まえ、家庭裁判所の公務員は、民法改正の趣旨や国会でのやりとりさえ把握すれば、旧来の判断基準を変更するものと期待していました。しかし、従来の考え方を改める気がない者が存在します。
(B)の調査官報告書などは、国会において法務大臣が提示した基準を完全に無視し、真っ向から挑戦する内容です。「相手方が合意なく当時の監護環境を変えたことだけをもって、申立人に事件本人を引き渡す根拠とするには足りない」「面会交流の制限だけをもって相手方の監護能力が不十分であるとまでは言い難いところがある。などと書いていますが、これが上述の国会で提示された法解釈に反することは言うまでもありません。
これは、明らかに違法行為であり、裁判所の公務員が法に従わないなどということはあってはならないことです。
確かに、民法第766条の条文の改正は、これまで曖昧であった当該条文の趣旨を「明確化」したものに過ぎず、新たなルールを作成したものではありません。しかし、条文解釈の基準が法改正時の国会において法務大臣により明確化された以上、その解釈基準に沿って今後は当該条文を適用すべきであることは言うまでもなく、また、これまで裁判所において利用していた基準のうち明確化された解釈基準に対立する部分については、国会で示された法解釈を覆えさなければならない特段の合理的理由がない限り、当然その適用は止めなければなりません 。(脚注1)
もし、裁判所の公務員が、自分にとって「不都合」な事実は無視し、好きなように法律を解釈できるのであれば、国会で長時間にわたり法案を審議する必要は全くありません。国会など不要です。
「司法権の独立」とは、裁判所(司法府)が政治部門からの不当な介入を防ぎ、独立して自主的に活動できることを保障するための配慮であり、裁判所の公務員が法律に根拠を持たずに自らの主観に基づき恣意的に決定を下してよいということでは決してありません。今や何ら法律に根拠を持たない独自の解釈に基づき監護者の決定や面会交流の決定がなされることになるのであれば、それは法治国家を司法府自らが否定するということになります。
(A)や(B) の事例に見られる家庭裁判所の公務員の態様は、民法改正前であれば許容されていたかもしれませんが、彼らは状況が全く変化したにもかかわらず、従来のやり方を考えもなく踏襲し、その結果、越えてはならない一線を越えてしまったのだと言えます。
一介の家庭裁判所の公務員が、改正された法律の立法趣旨を一切無視し、また国会の審議も一切無視するということは、国権の最高機関たる立法府と法務大臣を冒涜するものであり、民主主義に対する挑戦です。
家庭裁判所の公務員が公権力の行使を行えるのは、「法に基づき」職務を遂行しているからです。そして、法は、国民の代表たる国会議員が採択するというプロセスを経たことで正当性を有しているのです。憲法で謳うところの国民主権はいうまでもなく、司法にも及ぶものです。
家庭裁判所調査官の報告書などから透けて見えるのは、立法府や法務大臣をないがしろにする家庭裁判所の公務員たちの独善的かつ傲慢な態度です。このような態度を有する職員を、いつまで最高裁判所は放置しておくのでしょうか。
民法が改正され解釈の変更がなされたにもかかわらず、それまで利用してきた裁判所独自の運用基準を根拠なく適用する調査官は、裁判所職員臨時措置法で準用するところの国家公務員法第82条第1項第2号「職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合」に該当することは明らかです。
憲法第15条第1項には「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定してあります。
これらの規定に従い、私たちは、一国民として、法律を無視し、親子の絆を平然と引き裂く調査官に対し懲戒免職その他の処分を下すことを要請します。
(2)「子どもを連れ去った親に親権・監護権を付与する」という結論ありきの運用を変えない
子どもの監護者指定に関する家庭裁判所の調査官や裁判官の書く文章は、必ず最後は、「これまでの事件本人(=連れ去られた子ども)への相手方(=子どもを連れ去った親)の監護の態様には問題が認められず、また、現在も相手方が監護し、事件本人もその監護環境に良好に適合していること等も考慮すると、事件本人の監護者を相手方に指定することが相当である」という結論で終わります。これが、いわゆる「継続性(現状維持)の原則」です。
これは、民法のみならず、いずれの法にも根拠を持たず、単に家庭裁判所が運用上採用していただけの基準です。
そして、当該基準については今回の民法第766条の改正の国会審議において法務大臣から明確に否定されました 。(脚注2)
なぜ、この原則を家庭裁判所の公務員が採用するかと言えば、「効率よく事件を処理できる」からです 。(脚注3)すなわち、「子どもの利益」よりも「裁判所の利益」を第一に考え、自らの作った判断基準を優先させているのです 。(脚注4)
そして、「裁判所の都合」を第一に考えた「現状維持」との結論を導くために都合の悪い「事実」は捨象し、甚だしい場合は歪曲して記述してしまいます 。(脚注5)例えば、結論ありきで、子どもの利益などを全く考慮しないため、(A)(B)の事例で見られるように、臨床心理士などが意見書を出したり、小児科の医師が意見書を出しても完全に無視されます 。(脚注6)ここから明らかなように裁判所の公務員は「専門的技術・能力」など全く利用しておらず、第三者としての「中立性・公正性」も全くありません。調査官らの意見書の中身は、民主的コントロールが全く及んでいない点で正当性がないのは明らかですが、それに対抗する言い訳としてしばしば言及されるところの「専門性」「中立性・公正性」も全くない以上、どんなに好意的に考えたところで「尊重すべき」文章ではないことは明らかです。
このような「事実」の歪曲等をおこなっている家庭裁判所の職員の態様を放置しておくことは裁判所組織への国民の信頼性を大きく失墜させることにつながるものであることを最高裁判所には是非認識してもらいたいと思います。
そして、「継続性(現状維持)の原則」を金科玉条とする家庭裁判所の運用こそが、一方の親による子どもの連れ去り・引き離し行為を引き起こしているとの認識は、近年では法曹関係者を含め離婚後の子どもの環境を研究する専門家の間で広がっています 。(脚注7)
すなわち、子どもの奪い合いが後を絶たないのは「裁判所が関わっているのに」のではなく、「裁判所が関わっているから」起こるのです 。(脚注8)
このような現状を受け、今回の民法第766条の改正が行われ、そして、家庭裁判所の「継続性(現状維持)の原則」の採用を改めるよう、国会で再三にわたり法務大臣を始め、党派を超えて、多くの国会議員が批判したのです。
しかしながら、前述のように、家庭裁判所の公務員はそれを完全に無視し、(A)(B)の事例で見られるような意見を相変わらず出しているのです。
そして、民法改正後も家庭裁判所がこの原則に固執しているため多くの親子が未だに引き裂かれています。そして、民法改正後のこの数か月で自殺に追い込まれた親が少なくとも二人います。彼らは裁判所により殺されたようなものです。さぞかし無念だろうと思います。
人の命を殺めてまで守るべき「原則」などないはずです。これは明らかな人権侵害であり、下級裁判所の運用に強く抗議をするとともに、本質的な体質改善を早急に図るよう求めます。
(3)審判官は面会交流を制限するために「言葉遊び」をしている
非監護親は子どもとの交流のために、できる限りの時間とエネルギーを使い、必死に自分の気持ちを綴っても、監護親の面会拒否感情が強いと、審判官は面会の義務付けを避けます。その理由づけのために、非監護親が全身全霊を込めて書いた準備書面、陳述書を「無視」するか、文脈とは全く関係ない部分を抜き出し、「悪意」にその部分を繋ぎ合せ、面会制限理由を創作する一方、監護者の不適切な事実に関しては、「好意的」に解釈するか「放置」します。これこそが、牽強付会の「言葉遊び」です。
(A)の例で検証してみると、審判では、確かな証拠もなく、ありもしないDVがあったことを前提に話が進んでいきます。そして、当時1歳だった乳児がそのDVを見てトラウマとなっているという。署名の公開を拒むような医師の意見書を採用し、別居から4年以上たった今でも監護者が精神的に不安定であり、子どものトラウマの治療に数年を要するから、今後数年面会を制限するのが相当であると、実質面会の禁止をしているのです。そのような名無しの医師の意見書が提出されていることも申立て本人には知らされず、審判をみて初めて知るような状況でした。その抗告審では、申立人は、名無しの医師の意見書に対し、その診断方法の不備を指摘した小児科医師の意見書、臨床心理士による面会交流の具体的導入方法の意見書を提出したが、全く無視されています。そこには、反論する意見書よりも名無しの医師の意見書を優先する理由すら記されていません。
裁判官が面会交流を実現しようと働くのではなく、目の前のある問題を手早く「処理」するために、面倒なことは避け、面会を制限していると指摘をされても、そのそしりを免れぬ事例です。
(4)審判官は調査官調査を面会制限する材料に使う
調査官調査は審判官の命令の範囲内でしか、実施もその内容をも決めることができません。彼らができる調査は、「監護親の主張を聞くこと」、「監護の様子の聞きこみ調査すること」位です。審判官は、自らが望む調査を調査官に命じ、それを客観的、科学的調査だとして、都合よく利用することが可能となります。
調査官に求められているのは、その報告書の中で、監護者の面会拒否感情が強いことを示唆すること、面会を喜んでいないことを表現した幼児や児童の言葉を書き留めることなどです。そして、結論には、「双方の親が子どものことを考え配慮しながら、監護親が同意するのであれば、面会交流をすることも可能と思われる」と締めるのです。
調査官にそう報告してもらえれば、あとは審判官の意図通りに進みます。何故なら、この短文の中にも、①「監護者が同意するのであれば」と、②「双方の親が子どものことを考え配慮しながら」と二つの巧妙な仕掛けがあるからです。監護親が面会に同意しなければ、調査官調査を重視したとして、いとも簡単に面会制限ができてしまいます。また、そもそも相手方にもコンタクトできない、子どもとも会えない親は、面会交流のために配慮のしようがないのに、非監護側が面会交流を拒むのは監護親の身勝手だと指摘すれば、「夫婦の葛藤が激しいから面会は困難」だと「言葉遊び」ができてしまうのです。
ついには、非監護者は審判文の中で、「現段階で面会交流を義務付けるのは、子どもの福祉に適わないと考えるのが相当である」と、紋切り型の理由を言い渡します。この一連の流れは、裁判所が、夫婦の葛藤が激しいことを理由に面会交流制限をしていることを示しており、法務大臣の発言を無視していることは明らかです。しかも葛藤そのものを、裁判所の公務員が演出しているという点で非常に悪質であると思います。
これに近い表現を(B)の中から拾ってみると、「面会交流の制限については、別居後も面会交流が行われていたところ、紛争の拡大により一時的に中断していると捉えることができる。一般的に、当事者が激しく争い、子に影響が及ぶ可能性のあるような場合には子の福祉を考えて面会交流を中断する可能性がない訳ではない。そのため、本件においても、面会交流の制限だけをもって相手方の監護能力が不十分であるとは言い難いところがある」と、二重否定を利用し調査官も自らの責任を回避しながら、審判官も面会制限を肯定しやすい状況を作り出すカラクリになっていると言えます。
(5)調査官調査が親子の再統合を目指すものになっていない
民法改正の公布により、調査官調査が従来よりも行われることが多くなったことは私たちも把握していますが、結論は民法改正前と全く変わっていません。結局、「子どもを連れ去った親」に「親権・監護権」を与えるための理由付けとして、「入念な調査をした結果」との弁明ができるようにしているだけです。その意味で更に巧妙になったといえます。
調査官調査を開始するまでに何回も調停を重ね時間を経過させ、「継続性(現状維持)の原則」を適用しやすくします。その間の親子交流は途絶えたままとなり、仮にその後、子どもとの面会が再開されたとしても、子どもはよそよそしくなってしまうことが多く、元の親子関係に戻すのに相当の時間を要します。そして、非監護親の悪口を吹き込また子どもの場合(片親疎外と言われる行為)は、非監護親に敵意を示したり、場合によっては泣き出すほどの恐怖感情を植えつけられてしまったりすることもあり、この状況までいってしまうと、もはや元の親子関係に回復させることが困難となってしまうのです。
調査官調査はするものの、結論では(4)で指摘したように、「双方の親が子どものことを考え配慮しながら、監護親が同意するのであれば、面会交流をすることも可能と思われる」と締められます。その成果物も、典型的な雛形に、疑いようのない事実と、聴き取り調査結果を入れると完成してしまうようなもので、素人でも一日で作成可能なものです。にもかかわらず、調停が開始されてから、調査官調査が終わるまでに一年以上かかることも珍しくないのです。
(A)の調査官調査のように、監護者の言い分・幼稚園の先生の言葉・家庭での子どもの様子を書くだけで何ら意見がないもの。(B)のように、子どもと会えない親は早期の面会を強く主張するしか方法がないにも関わらず、非監護親の正当な主張を「葛藤が激しい」という言葉に置き換え面会拒否を認める理由として認めてしまうもの。親子の交流断絶期間が長引けば、子どもは監護親の影響を強く受け、非監護親との面会に積極的になれないことは仕方がないのに、幼児や児童の表面上の言葉を鵜呑みにし面会交流を制限するもの。これらの三パターンでほとんどが占められています。
私たちは、未だもって、調査官調査によって、親子再統合が前進した事例を知りません。つまりは、親子再統合にとって、調査官調査は何の効果も発揮せず不要であるとの結論に達さざるを得ません。子どもと会えないと申立てられたら、「それは大変だ。すぐに会いなさい」と、裁判官が「エマージェンシーコンタクト」を命令し、すぐに面会を開始する諸外国とは雲泥の差です。
法務大臣は、国会において「家庭裁判所でそういう合意(=面会交流や費用の分担など)をつくるときに、家裁には調査官がいますから、調査官は、その親子の再統合というようなことまで考えていろいろなことをやりますから、私としては家裁調査官の仕事に大いに期待をしたい」と答弁していましたが、(B)の例を見て明らかなように、その期待に家庭裁判所の調査官が全く応えていないのは明らかです。
調査官調査をすると、いたずらに親子交流が絶たれる期間が延びるだけで、親子再統合に逆行しているのが現実です。したがって、面会交流の申立てがなされたら、すぐに面会交流を開始し、調査官調査はその後の経過を観察する同時進行型にすべきであると考えます。
(6)調査官調査が調査対象である家族に対し全く無責任である
調査官調査が、親子再統合になっていないだけではありません。調査という行為が、政府における「審議会」のような隠れ蓑になっていることがもう一つの問題です。調査官は「自らの意見は最終的なものではない」と主張し、審判官は「調査官の意見によると、・・・」と記述し、責任の所在を曖昧にします。自らの判断が親子の仲を引き裂き、その親子の人生を狂わせていることに対する罪の意識を感じなくて済むような巧妙な仕掛けになっているのです。
監護者を連れ去った側の親とした場合、その後の面会交流が困難になることが容易に予想されますが、その手当ては何も考えません。抗告すると、親子交流は大切であるからとは記載しますが、その具体的な方法は、「家庭裁判所の力を借りて時間をかけて取り組むべきである」とたらい回し同然の有様です。面会交流を制限したり禁止したりしておいて、親子交流が断絶してしまった親子のその後の人生などおかまいなしです。また、(B)の事例のように、「子どもが海外に連れ去られるおそれがある」と何度も訴えているにもかかわらず「具体化していない」の一言で切って捨てます。裁判後に、子どもが外国に連れ去られようが、一部の家庭裁判所の公務員にとっては「どうでもよいこと」です。その無責任な対応には心の底から憤りを感じます。
このように、子どもの将来を決めてしまうような一大事を、対象になる子どもとたった数時間会っただけで、全く責任も感じず軽々しく判断してしまうような家庭裁判所の公務員たちは、家族の問題に立ち入る資格はありません。
以上、二つの事例を取り上げて説明しましたが、私たちのホームページで企画している『家裁通信簿』には、日々、調停や審判の評価が寄せられています。同時に審判書や調査官調査を収集中です。不当な審判書や調査官調査書を次々に報告する必要がないよう、最高裁判所におかれましては、以下の点を考慮して、下級裁判所への指導を強めていただくことを要望します。
| 1. | 家庭裁判所調査官は、子の「連れ去り」「引き離し」への認識を改め、これらの行為の子への悪影響を前提とした調査を行わなければならない。「連れ去り」「引き離し」が存在したと考えられる時には、「引き離し期間」の片親疎外の影響を考慮し、単に現在の子の状況を調査するのではなく、別居前後の子の状況把握に努め、その結果を基に判断しなければならない。 |
| 2. | 子どもの健全な成長を考えれば、別居・離婚後も双方の親に会い、双方の親の影響下で成長することが望ましいのは明らかである。そのためには、親権者や監護権者は、相手方への寛容性がより高い親に与えられるべきものである。それは、寛容性が高い親に与えることで、双方の親が子どもとの安定した関係を維持しやすくなるからである。 |
| 3. | 未だ離婚しておらず、監護能力に遜色がなく、法的に親権・監護権の制限を受けていない別居親の場合には、監護親・非監護親という概念ではなく、主監護親・従監護親という概念を導入すべきと考える。面会交流家族の再同居の可能性も考え、できる限り双方の親の監護日数を平等にすべきである。不幸にして離婚となるにせよ、双方の親から平等に愛情を受けることが、子の福祉に叶う唯一の方法なのである。 |
以上
添付資料
(A)事件の関連資料一式
(B)事件の関連資料一式
(脚注1)
「わが国は、…判例に先例拘束性を認めず、裁判官は法律にのみ拘束されるとしている。…すなわち日本国憲法七六条三項は『すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される』と規定しているから、わが国の裁判官は、上級裁判所の判例であろうと、あるいは過去において多くの裁判所がくり返し採用してきている先例であろうと、何らこれに拘束されるものではない。…(しかし)実際には判例はある程度拘束力をもっており、判例法が存在する余地があるのである。もっとも原則として、制定法が中心であるから、判例法が成立するのは、第一には法に規定が存在しない場合であり、第二には法に規定はあるがその解釈に争いがあり、判例法によって解釈を統一する場合であり、第三にどうしても制定法の規定が社会の発展に応じきれなくなったような場合に、この制定法の規定と異なる解決をなす場合であろう」
(「法学入門(第4版)」末川博著)
(脚注2)
「いわゆる継続性の原則、これは今言ったようないろんな事情から、合意ができる前にあえて無理して子を移動させてそして自分の管理下に置けば、後は継続性の原則で守られるという、そういうことはやっぱりあってはいけないと。全てのことがもし同じならば、それは子供にとって環境が変わることが必ずしも好ましいわけじゃない、同じ環境の下で育つ方がいいとは言えますが、継続性の原則があるから、だから連れ去った方が得だと、そういうことがあってはいけないことは御指摘のとおりだと思っております」
(平成23年5月26日 参議院法務委員会「法務大臣答弁」)
(脚注3)
「家庭裁判所の裁判官は非常に忙しく、事件を効率的に処理しなければならない。また、子どもの事件に関して言えば、家庭裁判所はできないことが多い。家庭裁判所には法廷外の世界に対する実質的な影響力が少ないにもかかわらず、国家機関の威厳を保ちながら、いかに子どもの福祉を実現している体裁を整え、効率よく事件を処理するかが、日本の家事事件制度における課題である。とすれば、子どもの現状を追認することが一番確実かつ簡単にできる事件処理方法となる」
(「子どもの連れ去り問題-日本の司法が親子を引き裂く」コリンP.A.ジョーンズ著)
(脚注4) 「日本が批准する『子どもの権利条約』に、『父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係および直接の接触を維持する権利を尊重する』と規定されているにもかかわらず、裁判所は自ら作った判断基準を優先させている。すなわち、日本では『子どもの利益』よりも『裁判所の利益』を優先し、子どもに関する裁判運用は裁判所にとって都合よくなされている」
(「子どもの連れ去り問題-日本の司法が親子を引き裂く」コリンP.A.ジョーンズ著)
(脚注5)
「家庭裁判所が、どういう情報をもって決定しているか外からはチェックできない。そのため、当事者の一方がウソを言っているとしても、もう一方の相手は、それを追求したり反論することが不可能である。また、子の監護事件における審判などの法的判断は、結論を先に出して、それに見合った事実認定をしていても、『非公開・非訟』という制約のために、当事者は対抗することが非常に難しい。そのため、現状が子どもにとっていい、という結論を打ち出すための事実認定を裁判所は簡単にできてしまう。」
(「子どもの連れ去り問題-日本の司法が親子を引き裂く」コリンP.A.ジョーンズ著)
(脚注6)
子どもをめぐる裁判事件になれば、児童心理の専門家より調査官の方が”権威”になることが少なくない。一般の人からすれば、それはおかしいではないかと思うかもしれないが、家裁の組織論からすれば、むしろ合理的である。児童心理学者や精神科医は子どもの全体的な心理状態を第一に考え、依頼者が達成しようとしている目的を第二に考えて見解を述べるだろうから、「子どもの利益、子どもの福祉」を重視した見解になるが、それは必ずしも裁判所が事件処理に使える内容ではない。一方、調査官は裁判所に雇われ、裁判官の事件処理業務を補助するために働いている。調査官は法律と手続きで裁判所に何ができるかを踏まえ、忙しい裁判官に代わり、事件処理に即した事実調査をしてくれるのだから、裁判官が調査官の報告の方を優先するのは当然である。
(「子どもの連れ去り問題-日本の司法が親子を引き裂く」コリンP.A.ジョーンズ著)
(脚注7)
「米国では、別居する前に、面会交流を含む養育計画の取り組みをしないといけないので、夫婦の一方が相手との話し合いもせずに子どもを連れて勝手に別居することは、子どもの「拉致」に当たり、犯罪行為とみなされる。しかし、日本では、母親が子どもを連れて勝手に家を出ることは、違法行為とみなされないどころか、その後の親権・監護権の争いにおいて『監護の継続性』との視点から、よほどのことがないかぎり母親に継続的に親権・監護権が付与されることになる。人は、裁判に持ち込まれた場合に、どのような決定がなされるかを見越して行動する。したがってこうした判例の下では、次々と判で押したような事件が起きても不思議ではない」
(「離婚で壊れる子どもたち-心理臨床家からの警告」棚瀬一代著)
(脚注8)
「本来は子どもを守るはずの裁判所が離婚事件等における裁判運用で子どもの連れ去り・親子の引き離しを助長し、場合によっては肯定までする一種の『拉致司法』が形成されていることこそが、子どもと片方の親をはじめ、その祖父母や他の親族との絆をズタズタにされ、子どもとその親の生涯にわたって大きくネガティブな影響を与えてしまう悲劇を招いている」
(「子どもの連れ去り問題-日本の司法が親子を引き裂く」コリンP.A.ジョーンズ著)